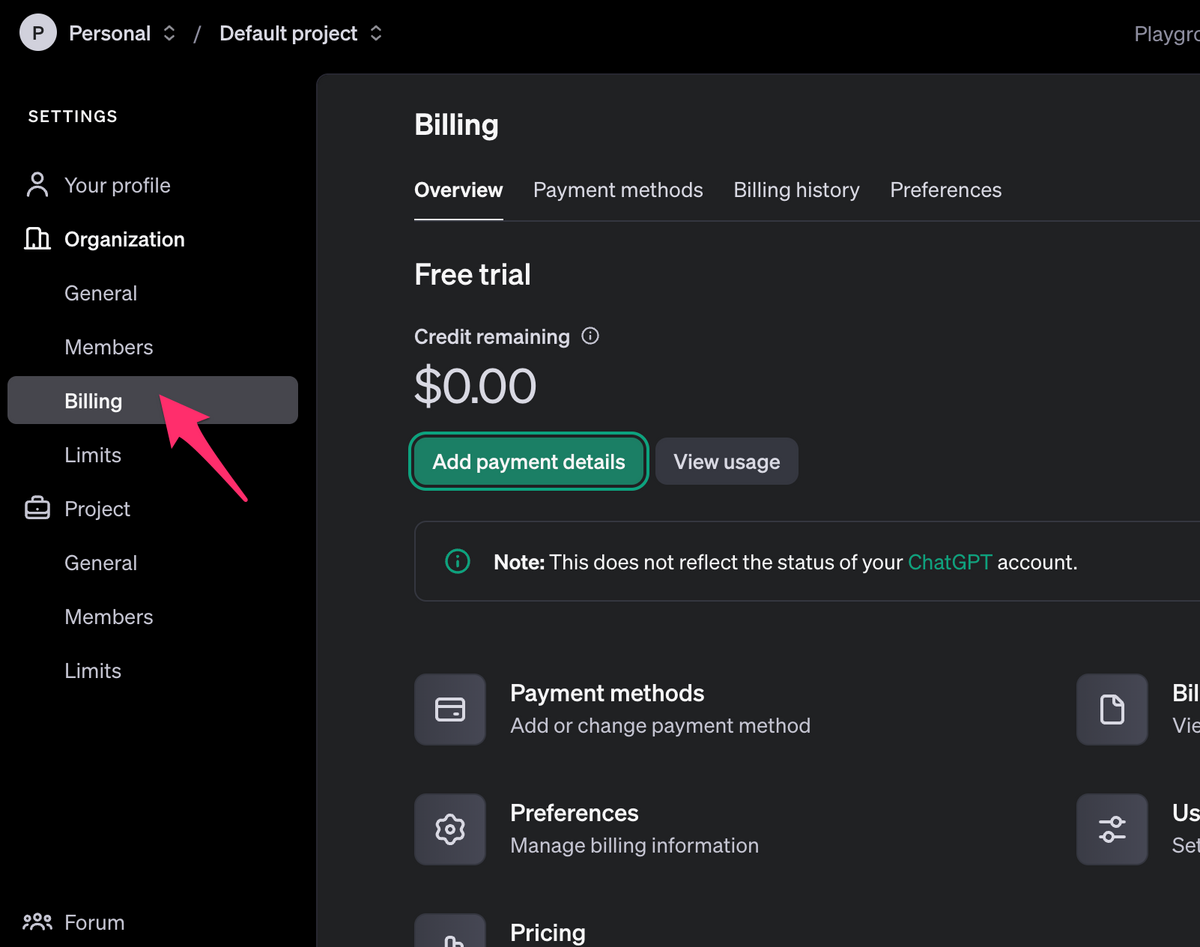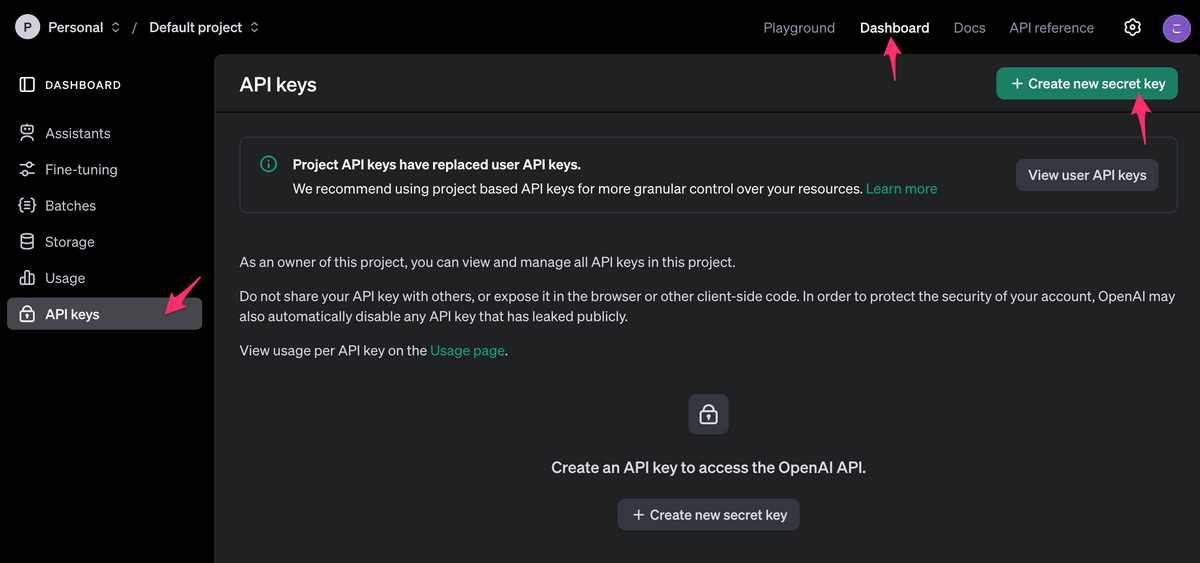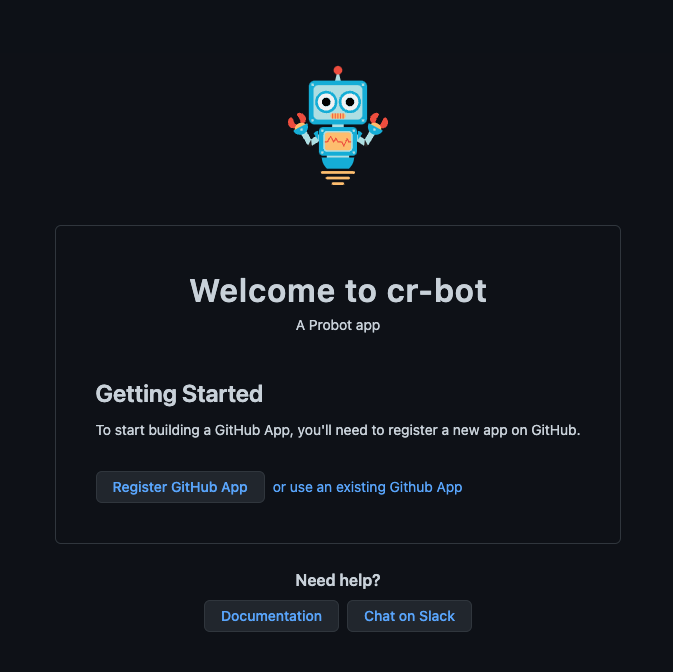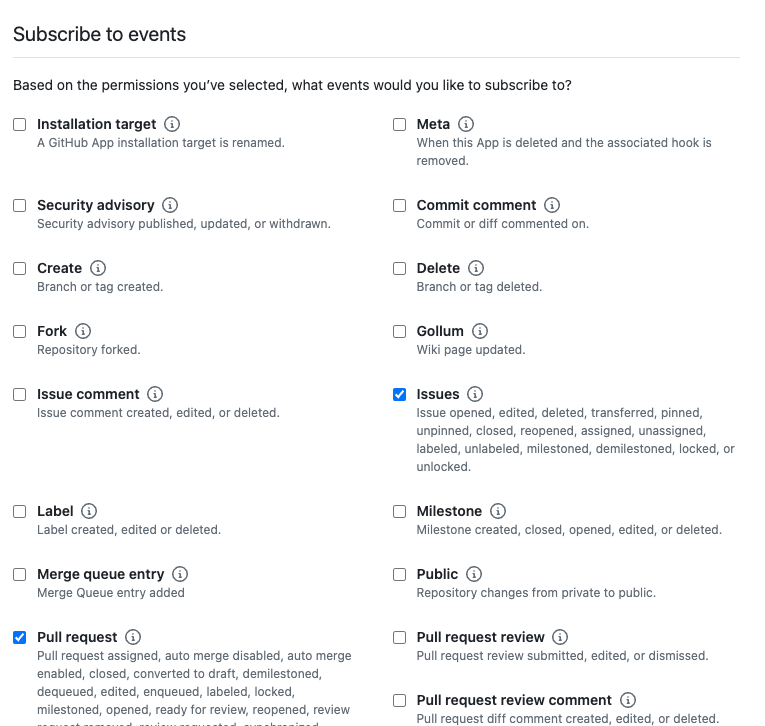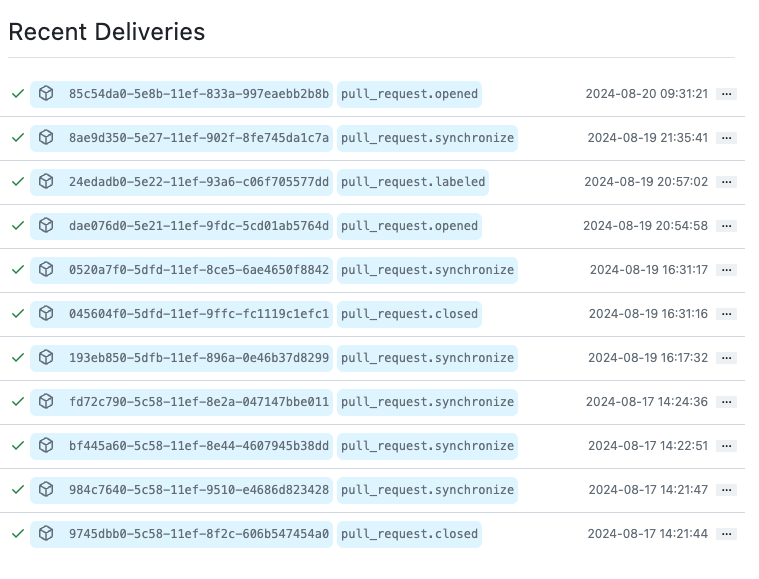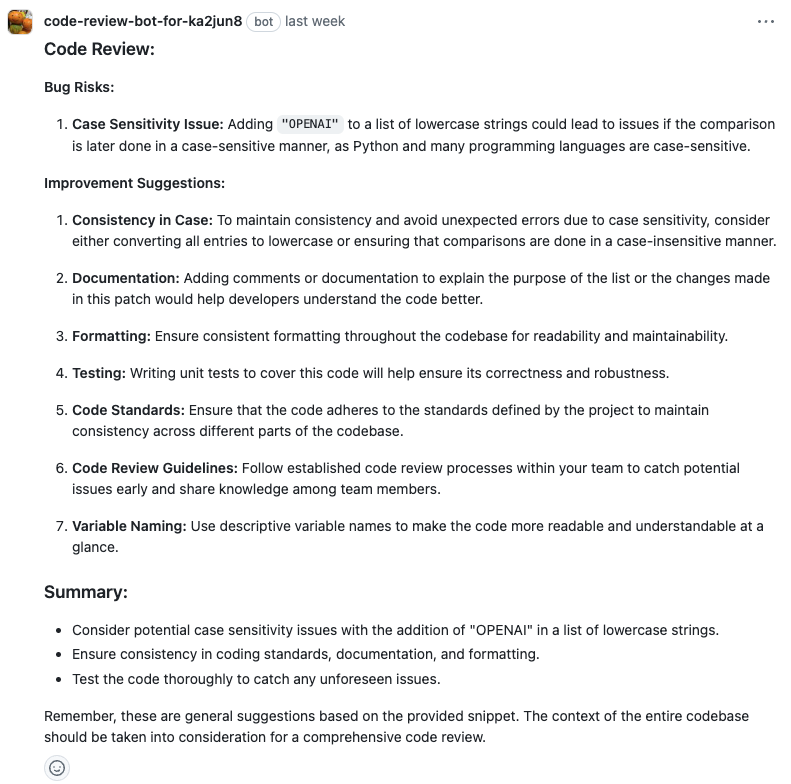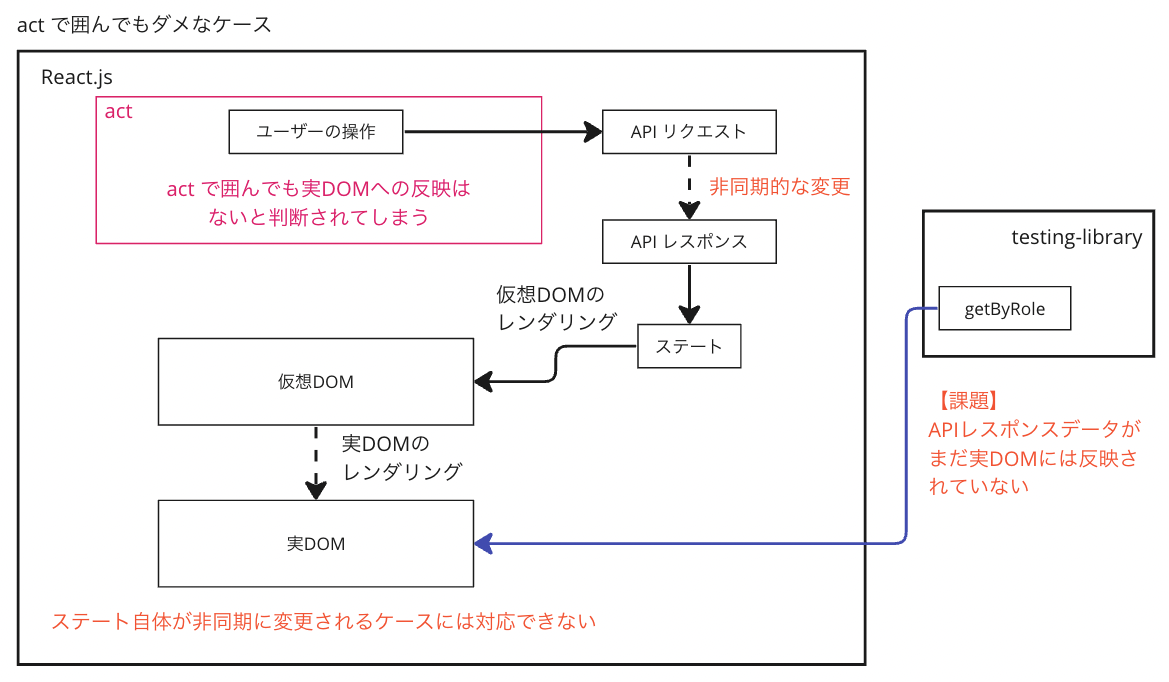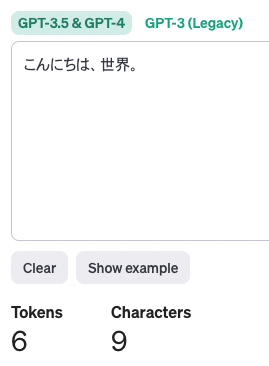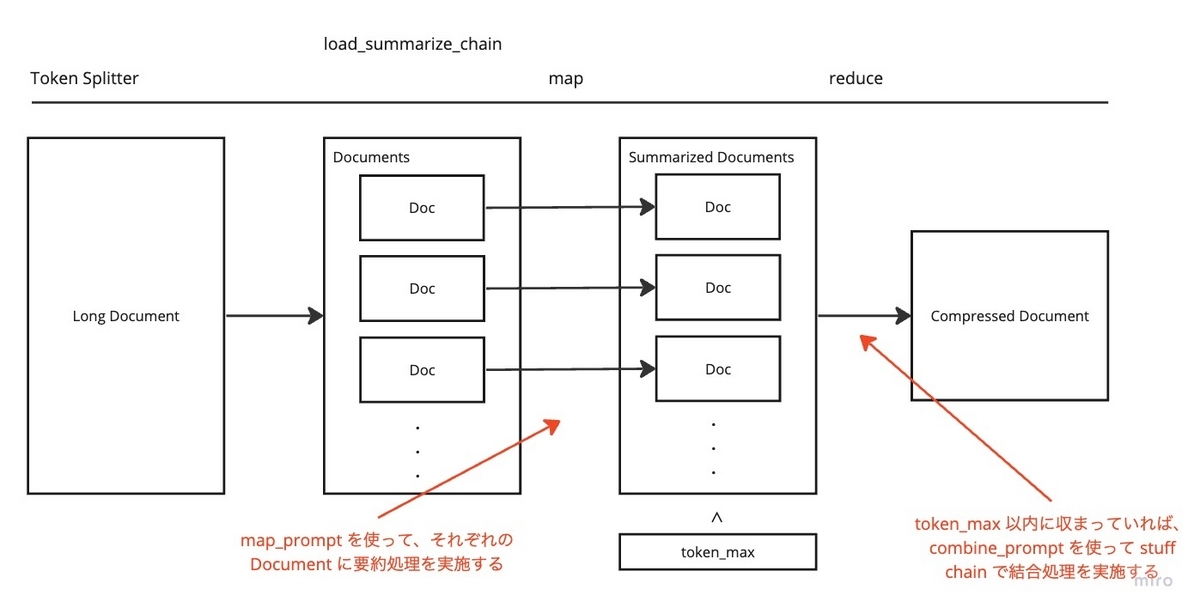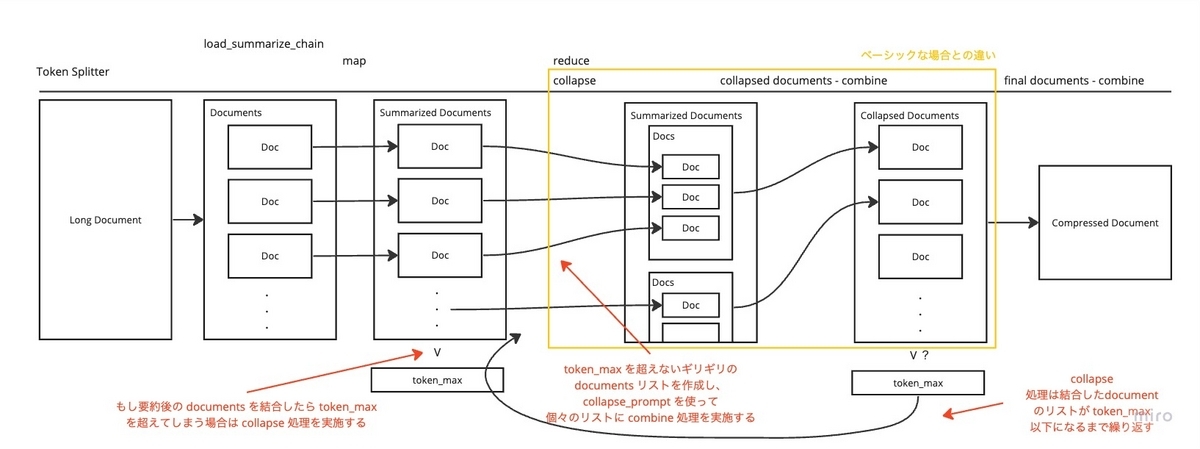2025年はいろんなことがあった。
第二子👶
妻が第二子を妊娠した。 妊娠がわかったのが2月。
一人目のときもつわりがひどく、 二人目も残念ながらつわりが出た。
今回は一人目もいてのことなので、家事育児が妻が思うようにできなくなってしまった。
結果として、急遽自分が1ヶ月仕事を休むことにした。
幸い会社の制度で休めたのでよかった。 職場には迷惑をかけたが、休んで本当によかった。 (というか休む制度がなかったら最悪仕事を辞めていたかもしれないなと思う)
つわりのひどい時期をだいぶサポートできたが、1ヶ月では休みが足らないくらいではあった。 (つわりは治らなかった)
基本的に家事育児をしてたら一瞬で時間は過ぎ去り、1ヶ月の間、自己研鑽には全く時間を使えなかった。
中古戸建を買って引越した🏠
子供が二人になると確定し、2LDKのマンションに住み続けるのは困難になった。
マンションは、3LDKだとしてもリモートワークのスペース確保を考えたり、車を持つことを考えると、なかなかマンションには決められなかった。
戸建となると、土地と上物で値段を考えると都心からの距離が離れてしまい、決めきれない。
かなり迷ったが結果的に関東を離れて地方移住した。
家は中古戸建にした。 地方とはいえ、アクセスや広さを考えると新築戸建を建てる余裕はなく、中古の戸建てを購入した。
いろいろ物件をスーモで見て問い合わせしまくった結果、いい家ではなくいい不動産屋さんに巡り会えたのがデカかった。
不動産屋さんにいろいろ仲介を頑張ってもらって、住みたいと思える中古戸建にであえてよかった。
出産というリミットがあるので決めきれた部分も大きい。 保育園の転園は必要になるが、学校の転校よりはマシと判断。
学校周りで言えば、お受験を避けたくて地方にした部分もある。
実家には近づいてはいるが、実家の近くではないので依然として親を毎日のように頼れる状態ではない。
都心にも出られる範囲の地方を選んだ。 (だから土地が結構高かったのもあると思う)
中古戸建をいざ買うまでの壮絶なエピソードは別で書く予定。
7月末に物件の引き渡し、8月に引っ越しとなった。
会社の夏季休暇に合わせて暑い中だったが、時間をかけて荷造り・荷解きして引っ越しができた。
お互いの両親に頼りつつ、最低限住めるような整理ができた。 妊婦と小さい子供がいながらの引っ越しは大変だなと思った。
妻は引っ越しの時期には産休に入っていて、引越しが終わって少しして里帰りになった。
一人目は8月の引越し月は転園に失敗(近くの保育園に空きがなかった)し、役所に相談したりして9月から小規模保育園に入ることになった。
とはいえ、ママが里帰り、パパはフルタイムで仕事という状況もあり、1週間慣らし保育したら、上の子は一緒に里帰りしてもらった。
後述するが、赤ちゃんが生まれてからは上の子だけ戻ってきてパパとワンオペ保育園生活となる。
第二子の出産👶
10月初旬に第二子の出産があった。 バタバタしつつ、ほとんど予定日通りに出産となった。 一人目と違う産院で、無痛分娩を選んだ。 無痛分娩にも種類があり、人にもよるとは思うが、割と痛みがある出産になった。
仕事は11月〜1月末までを育児休職に、10月後半は有給という形で休むことにした。 生まれてからは義実家でママと赤ちゃん、新居でパパと長女という形態を採った。
新居でママと離れてパパと暮らしながら、慣れない家と慣れない保育園に通う生活は3歳には相当ストレスだったと思うが、とてもいい子に頑張ってくれた。
今はもう1ヶ月検診を無事に終えて、里帰りから新居に戻って家族4人の生活になっている。
子供二人と育休生活
一人目がいるので、育休とはいえ赤ちゃんの面倒ばかりを見ているわけではない。
基本的に、むしろママは母乳をあげる使命があるので、必然的にママは赤ちゃん、パパはお姉ちゃんの面倒を見る感じになっている。
上の子がいない保育園の間に両親二人がかりになる沐浴は済ませたくて、14時半ごろから沐浴するようにしてる。
休んでから知ったのだが、育休中は保育時間が短時間になってしまうため、基本の預け入れが8時〜16時になる。
お迎えに行く時間も考えると、15時半にはお迎えに行くことになるので、ほとんど午後はお昼ご飯を食べたらすぐ沐浴で、お迎えになる形。
上の子が帰ってきたら寝るまでつきっきりなので、21時か22時くらいまでは両親ともにいてもノンストップで時間が過ぎ去っていく。
仕事に復帰できる気がしない…。
考えたこととまとめ
二人目ができたことで、これからの人生の舵取りを考えざるを得なくなった。 0か100かではないものの、住む場所によって家庭に重きを置くか、仕事に重きを置くかは考えた。
地方移住でキャリアを登るのはとても難しいだろうなとは思いかなり悩んだものの、自分のキャリアよりも子供にとって良いのはどちらか考えて決断した。
一人目の時の育児休職は、育児にバタバタしてるだけだったが、二人目の育児休職はちょっと違っていた。
もちろん一人目の育児も増えているので大変さは倍増しているのだが、どちらかというと赤ちゃんへの接し方に対して気持ちに余裕がある。
一人目のときから授乳以外すべてできるようになっていたので、二人目でもほとんど自分だけで赤ちゃんの世話はできる。
一人目の面倒も自分だけで見られるし、里帰り後半の数週間はワンオペで上の子を見ていた。
その結果、二人の子供に接しながら感じたのは、とてつもなく子供たちが可愛いということだった。
特に上の子は、平日は、朝起きてすぐ保育園に送ってしまって、夜仕事を終えてから少し顔を見るくらいの生活だった。
育休ワンオペ期間は、保育園にお迎えして、お風呂やご飯、一緒に遊ぶ時間を過ごせて、3歳になってこんなにできることも増えて表現が豊かになったんだ、と毎日感動した。 (もちろんアホほど怒れることするし、叱ることも多いのだが…)
育休を取らなかったらこれが味わえなかったのかと思うと、本当に育休をとって良かったと思うし、仕事復帰したら見られなくなるのかと思うと、とても悲しい。
そういったことも踏まえて、自分は仕事以上に子供と接する時間を増やしながら、人生を歩んでいくことになるんだろうなと思う。
キャリアで言えば(副業とか対外活動してないので当たり前なのだが)、一時期に比べて外からお声がかかることがほとんどなくなった。
これに加えて出社回帰の中、地方移住しているので、もはや選ぶような転職は絶望的な気もする。
そんな中で自分がより理想的に、どういう仕事のキャリアを描いていけるかは、自分としても楽しみだったりする。